bodymakerptです。Follow @bodymakerpt
今回は、異常歩行シリーズの第五弾です。その名も間欠性跛行。あまり聞きなれない言葉の方もいるかと思いますが、医療従事者に関しては、一度は聞いたことがあると思います。
ではどうぞ!
間欠性跛行とは

間欠性跛行とは、歩く時間・距離が長くなるとふくらはぎなどの筋肉に痛みやしびれをきたしてしまう跛行です。少し休憩する・体を前かがみにする・座る等で症状が軽快し、また歩くことが出来るという特徴もあります。
間欠性跛行と関連疾患
間欠性跛行を引き起こす疾患はいくつかあります。
①脊柱管狭窄症
リハビリでは、この疾患はよく聞きます。高齢者でこの脊柱管狭窄症に罹患している人は、比較的おおいと言われていますが、意外と知名度が低い疾患の一つです。基本的には退行変性と呼ばれる加齢による関節や骨の変化によって脊髄が通る脊柱管が狭くなることで神経症状が出てしまうと言われています。
②血管性
・閉塞性動脈硬化症
動脈硬化が原因となり、血管の狭小化や血流の悪化により、組織・細胞が酸素不足になってしまい、痛みやしびれを引き起こしてしまいます。
・閉塞性血栓血管炎
バージャー病と呼ばれる難病が原因で起こる末梢血管の狭小化や血栓の形成により、組織・細胞が酸素不足になってしまい痛みやしびれを引き起こしてしまいます。
関連記事↓↓
リハビリと理学療法
ここでは、脊柱管狭窄症の間欠性跛行について行うリハビリ・理学療法について簡単に紹介します。
①物理療法
温熱療法・けん引療法・電気刺激療法などを使用して、症状の緩和や軽減を図る事があります。痛みに応じて強度を調節する必要があり、逆に悪化させないように注意が必要です。
②理学療法
脊柱の特徴として、体を反らせると脊柱管は狭まり、脊髄を圧迫してしまい痺れや痛みがでてしまうリスクが高くなると言われています。
関連する筋肉として、多裂筋や腸腰筋が固くなることで、骨盤の肢位によって腰部の脊柱は伸展を矯正されてしまい間欠性跛行の原因になってしまいます。その他、腹筋の筋力低下や腹圧の低下によっても腰部の脊柱は伸展してしまう可能性もあります。
つまり、多裂筋・腸腰筋のストレッチや腹圧をかける・腹横筋による骨盤の安定化をさせる事も有効です。また、両手杖やシルバーカーを使用して、体幹を屈曲位にする事で脊柱管の狭小化を防ぎながら動作を行う事ができる場合があります。
また、股関節の伸展可動域を広げていくことも有効です。歩行時に、股関節の伸展可動域が小さくなっていると腰椎の伸展や回旋によって代償を起こす方がいます。そのような伸展ストレスが繰り返し加わる事で間欠性跛行が起こってしまうケースもあるのではないかと考えられます。
バランスの面でも、背屈可動域や後方へのバランスの回復(後方への安定性限界の拡大)によっても、腰椎の伸展が緩和する可能性もある為、そこにも介入する意義もあるかと思います。
関連記事➡トレーニングの原則をサクッと解説
前回記事↓↓
関連のおすすめ動画↓↓
最後に
今回は以上です。
ランキングに参加しています。
下のバナーをクリックして頂けると励みになります。
こちら➡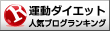
運動ダイエットランキング
こちらも➡![]()
にほんブログ村

 ブロトピ:今日の健康・医療情
ブロトピ:今日の健康・医療情